患者が治るための「私たちの方針」
○相談を通じて見えてきた医師の姿
○日本の医師の困った現状
○アメリカではどうなのか
○世界医師会の「医の倫理規定」
○重症から治った患者が思うこと
○治るにはどうしたらいいのか
○私たちの活動(完治した患者ならではの、医師が知らない知識と知恵を伝える)
○すべての患者さんへ
◎「患者の人権」に関する資料(医師は必ず読み、心に刻んでください。)
はじめに
誰でも知っているように、世界中の医療現場において、「最優先」なのは、「患者の人権」です。しかし日本の医療現場では、不可侵なのは「患者の人権」ではなく、「医師の権威が神聖で不可侵」という、明らかな倒錯がまかり通っています。
多くの線維筋痛症患者に処方されているベンゾジアピン系の薬は、覚せい剤と同じように依存性が強く、ほかの国では患者が依存(薬物中毒)に陥らないよう、連続投与は最大で2ヶ月などと規制され、患者の人権が守られています。しかし日本では、線維筋痛症学会も含め、多くの学会は、連続投与期間を規制せず、多くの患者が医師の処方によって薬依存になり、その結果、病気を治す以前に、いつ終わるとも分からない泥沼のような離脱症状に苦しむという、信じられないような深刻な事態を招いています。患者は当然、こんな結果を望んでおらず、医師の行った処方でそんな事態に陥ることも、予想すらしていません。患者から見て、まことに非人道的な事態です。実際に、医療現場ではどんなことが起こっているのか、寄せられた相談例から見てみます。

|
相談を通じて見えてきた医師の姿
まず、患者Aさんから来た相談の例です。(名前が特定されないように若干、編集しています)
「初めまして。こちらのNPO様の事は家族がネットで拝見し 素晴らしい活動をされていると感動し、この度、連絡させて頂いた次第です。
私は数年前から、繊維筋痛症と診断され、半年前に重症に陥りました。自殺を考えて毎日泣き明かす日々でした。痛みで眠れない日が数日過ぎ、地元の医者でそれまで服用していた薬では効かないため、必死に家族が名医と呼ばれる医師を探し、かなりの無理をお願いし、診察を受けました。
処方されたのは、抗うつ剤、効不安薬、てんかん薬、オピオイド麻酔薬です。(確認したところベンゾ系の薬も含まれていました。)
その日、数日ぶりに、寝る事が出来ましたが、その後、月に一度の受診を受けても、正直痛みは殆ど変らず。薬で睡眠できているから、自分を保っている感じです。
名医と呼ばれる医師は、忙しい時はろくに話も聞きません。薬の説明もありません。一番悔しかったのは、かけられた言葉です。
家族も私が悔しい思いをしている事を知りません。
「あなたは、日本人のこの病気の中の何万人の中から、選ばれた、選ばれし人!なのです」
「普通の人は、ここには来ません。普通の人は、頭痛薬を飲めば治ってるんです。」
「あなたは普通の薬では治りません」と。
私は、家族が感謝で頭を下げている中、一人、悔しい!その一言でした。
どの病気の人も、治りたい、普通と呼ばれる生活がしたい!好きで病気になった訳ではありません。「選ばれし人!」この痛みを経験していたら、絶対に言えない言葉です。選ばれたい人なんていない。私は、これが日本の名医なのか、と思ったとき、医者に絶望しました。
今も、毎日、痛みと薬の副作用と闘っています。どうか、心に寄り添える医師が、名医と呼ばれる日が来ますように。」
もう一人、Bさんの例をみてみます。
Bさんは、線維筋痛症(FM)になる前に、すでに化学物質過敏症(CS)でした。化学物質過敏症は病名で分かるように、わずかでも化学物質に触れると、めまいや痛み、吐き気などさまざまな症状が出る疾患です。BさんはもともとCS患者ですから、化学物質である薬も飲めません。しかしある病院で、ガンの診断を受け、薬を飲むのは怖かったのですが「命には代えられない」と思い、薬も使い、手術を受けました。そして不幸にもその後、線維筋痛症を発症したのです。
Bさんは私の「線維筋痛症から回復した患者のHP」を読んでいたので、線維筋痛症の専門医ならCS患者が薬を飲めないことは当然知っているはず、だから線維筋痛症の治療は薬以外の方法を考えてくれるだろうと思っていました。そしてBさんは、FM学会で有名なN医師の病院に行き、線維筋痛症の診断を受けました。
そしてBさんがN医師に、「CSなので薬は飲めない」と伝えたところ、しかしN医師は平然と、「化学物質過敏症といったって、薬を飲まないと治らないよ」と言ったそうです。
Bさんが通っていたCSの専門医は、患者が薬に過敏なことは熟知しており、治療にはビタミンなどを使います。ですからBさんは、まさかN医師がCSの自分にも薬を処方するとは夢にも思いませんでした。
とくにBさんは、N医師が「CSといったって薬を飲まないと治らない」と言ったのがショックでした。CS患者が、化学物質である薬を飲むとどれだけひどいことになるか、N医師がまったく理解していなかったからです。
「線維筋痛症学会の権威」というからには、私のHPに書いてあることくらいは当然知っているだろうと思い、Bさんは病院に行ったようです。一方、相談を受けた私は、N医師がこれらのことをよく知らず、また何の配慮もないことに、(それまでの患者さんからの相談から、たぶんそうだろうと思っていましたが)、期待して行ったBさんの手前、ものすごく恥ずかしい思いをしました。
薬を飲まないと治らない?本当でしょうか。
私が重症から完治し、「普通の人とまったく同じように走っている」動画を、YOU TUBEとニコニコ動画に投稿し、下記のHPにも入れています。
http://fmsjoho.in.coocan.jp/
何度も書いているように、私は治療やセルフケアに、薬をまったく使っていません。
一時、薬を飲んだこともありましたが、症状がひどくなるばかりで全く役に立ちませんでした。ですからN医師が言った「薬を飲まないと治らない」というのは事実ではありません。私のように、「薬を飲まなくても治る」ことも、よくあります。

|
日本の医師の困った現状
かつてN医師は、線維筋痛症学会の医師が集まっている前で、医師ではないカイロ・整体の治療家を排除する旨の発言をしたと、その場にいた医師の一人から聞きました。
医局や学会は封建的な縦社会で、N医師は治療ガイドラインなどを決める権限を持っているといわれるのに、そういう立場の医師が、カイロや整体の治療家を排除する発言をしたそうです。
しかしFMは私の例のように、薬なしでも治る病気です。確かに難しい病気ではありますが、薬なしで治る例があるのですから、学会は、薬以外の治療法も探らなければいけません。
FM患者は薬に過敏になることが多く、副作用が深刻な場合も多いです。患者が、薬以外の方法も健保の枠内で選べるように、整体などの治療家も学会に集め、患者が自分に合ったものをを←ケス選べるようにしておくことは、重要です。
整体などの治療家を排除するN医師の発言は、薬を使わずに治りたい多くの患者にとって、とてもとても迷惑で、本当に困ったことです。
私自身の回復例は、学会の前身である研究会で発表されていますが、私の症例発表のときにN医師は席をはずしたそうです。しかし重症患者でも薬なしの回復例があることを、N医師が知らないはずはありません。
私が回復した治療は、かなり多くの人が「やってみようかどうしようか」と迷っています。迷う理由の一つは、これがとても高額であるからです。そういう人たちから、「実際に効果がある人が大勢いて、そして高い費用がかかるのに、なぜこれが健康保険適用にならないの? 薬は健保でもらえるのに」という、怒りを何度も聞きました。なぜかを簡単にいえば、この治療が学会で(健康保険が使える)治療ガイドラインとして採用されないからです。
保険適用にするには、まず治験をして効果を確認したあとに厚労省に諮ります。しかしN医師が私の症例のときに席を外したように、「この治療を健保適用にする気はまったくない」と態度で示していると思います。
学会から整体治療家を排除したこともそうですが、今の学会は、薬を使わずに治療する気は一切ないというふうに見えます。そして、薬なしで治っている症例は見て見ぬふりで、なにより薬優先の方針が、この病気の泥沼化を招き、患者を困窮に陥れていると思います。
整体治療家が学会から排除されれば、患者は整体治療には健保を使えなくなります。もし、医師を通じて整体を受けられても、まず医師はガイドライン通りに薬を処方するので、整体だけ受けたくても患者はその前に病院の診察代や薬代も払わなければならず、非常に迷惑です。

|
アメリカではどうなのか
一方、アメリカの事情を調べてみると、アメリカのカイロプラクティック(整体)専門誌には、FMの記事がちゃんと載っています。内容もしっかりしており、「FMはCSS(中枢感作症候群、つまり中枢性過敏症候群)である」と説明がされ、FMがCSとよく併発することも載っています。下記をみてください。
私のHPから
http://fmsjoho.in.coocan.jp/page011.html#lbl03
日常の健康:線維筋痛症(2004年にアメリカのカイロプラクティック専門誌に掲載)
「線維筋痛症は、中枢感作症候群(中枢性過敏症候群:CSS)の中の一疾患であると認識されている」
つまりアメリカでは日本と違い、カイロプラクティック(いわゆる整体)治療家がFMの治療を行っており、だからこそ専門誌でもFMが紹介され、「FMはCSS」という正しい説明も載っているわけです。
ところが日本では、カイロプラクティック(いわゆる整体)治療を受けたくても、その前に病院で診察代を払い薬代を払わないと、整体治療は受けられません。そして日本の整体治療家はFMについての正確な知識を知りません。日本の患者はずいぶんと不利な状況に置かれています。
AさんとBさんの例を見てきましたが、次に彼らの医師が、世界医師会(WMA)の「医の倫理規定」に照らして「名医」かどうか判断したいと思います。
一般的な「名医」の定義では、患者から見て「名医」であるには、Aさんが完治していることが必須条件です。しかしAさんは、「月に一度の受診を続けて、正直痛みはほとんど変らず。薬で睡眠できているから、自分を保っている感じです。」「今も、毎日、痛みと薬の副作用と闘っています。」これからすると、Aさんはまったく治っていないと判断せざるを得ません。
次に世界医師会の「医の倫理規定」から、この医師が名医かどうか、みてみます。

|
世界医師会の「医の倫理規定」
(注)世界医師会(WMA)とは、各国医師会の連合体です。国の連合体が国連であるように、医師会の連合体が世界医師会で、当然ながら日本医師会も加入しています。世界医師会では、各国の医師が集まり、医師が守るべき「医の倫理規定」を定めています。当然ですが、これを守れない医師は名医どころではなく、世界医師会によると、是正勧告や排除の対象になります。
まず、「医の倫理規定」のなかの「ジュネーブ宣言」から(1948年に採択)
「私=医師は、(人権と自由を備えた)人の命に対し、最大限の敬意を持ち続ける」
*「最大限の敬意」とは、患者に対する最大限の敬意であり、「患者の命、人権を最優先する」ということ。
「私は、たとえ第三者(国や製薬会社など)の脅迫があろうとも、人権や国民の自由を犯すために自分の医学的知識を利用しない」
| *この原則が採択されるに当たっては、戦後にナチスの人体実験に協力した医師たちが裁かれた、ニュルンベルク裁判が起点になりました。第2次世界大戦で、人命を救うべき医師たちがナチスの人体実験に協力し、重大な人権侵害を行ったことへの痛切な反省から、世界中の医師が集まり、二度とこのような罪を犯さないように「医の倫理規定」が採択されたのです。 |
次に「ニュルンベルク綱領」(1947年)
上記のように、ナチスに協力して残虐な人体実験を行った医師たちは、ニュルンベルク裁判で「人道に反する罪」を侵したとして有罪判決を受け、死刑も言い渡されました。この裁判では、「人道に反する罪」には時効を適用しないことが確認され、ドイツ国内法には違反していなかった医師も、時間を遡及して有罪判決を受けました。
この裁判では、「あらゆる人が持つ人権(人間の尊厳)は、「自然法」から与えられているものであり、不可侵であり、現行法より優先される」ことが確認されました。
その結果、世界医師会でも、「自然法によって与えられた「人権」が国内法より上位」という原則が、戦後、すべての医師に求められる倫理規定になりました。
「あらゆる医学研究にあたっては、患者の利益が第一に考えられるべきであり、そのために、十分な説明が必要であり、それとともに、患者の自由意志による(自主的な)同意と、それとともに拒絶の権利が与えられる」
治療の現場も同じで、治療にあたっては、「医師による十分な説明と、治療を受けかどうかは、自由意志による患者の同意と、拒絶の権利がある」です。
世界医師会が定めた大原則はこの通りなのに、Aさんによれば、「名医と呼ばれる医師は、忙しい時はろくに話も聞きません。薬の説明もありません。」
薬の説明も何もないというのでは、この名医が「世界医師会の医の倫理規定」を守っているとは、とうてい言えず、世界医師会の規定に照らして、断じて「名医」ではありません。
「あなたは、日本人のこの病気の中の何万人の中から、選ばれた、選ばれし人!なのです」
「普通の人は、ここには来ません。普通の人は、頭痛薬を飲めば治ってるんです。」
「あなたは普通の薬では治りません」
この言葉は、意味不明です。まず、「普通の人は頭痛薬を飲めば治る」というのは事実ではなく、頭痛薬で痛みが治らない人はたくさんいます。Aさんが治っているのなら分かりますが、治らないのに「あなたは日本人のこの病気の中の何万人の中から選ばれた、選ばれし人!」は、何を意味しているのか分かりません。自分のような「名医」にかかれてラッキー!ということかもしれませんが、医師がそれを言うのは、Aさんが治ってからです。
Aさんはこれらのやり取りを通じて、「この医師は患者の苦しみをまったく分かっていない」と感じ、治療を続けても治る希望は持てそうになく、「選ばれし人!」という言葉に非常に傷つき悔しい思いをし、しかし医師の前ではその気持ちを押し殺さざるを得ず、医師が名医と呼ばれることに疑問を感じ、そういう現状に、絶望を感じたのです。
私もこの文章を見て、医師にはAさんを治せないだろうということ、このような状況でも、Aさんに「名医」という言葉が押し付けられていることに、非常な疑問を感じました。
ある医師が名医がどうかは、患者にしか分かりません。一方、製薬会社が、ある医師のことを「名医」と呼ぶことはあると思います。もし自社が作った薬が健保適用になれば、それだけで巨大な利益が上がります。FMに健保適用になったリリカは、いまでは全国で195万人に処方されているともいわれます。それは、リリカが健保で使えるようになったからで、それによって製薬会社が得た利益、今後もあがるであろう莫大な利益を考えれば、リリカを健保適用にまで持っていった医師は、製薬会社にとっては「凄腕の大先生」「大名医」でしょう。
リリカは、N医師がまず患者たちに、「リリカが保険適用になれば患者は治る、救われる」と力説し、友の会が全面的に治験に協力した結果、上記のように健保適用になりました。
N医師の言うようにリリカが本当にFMを治せる薬であれば、これが誰にでも処方できるようになった時点で患者は治り、患者の苦しみは終わり、社会復帰ができて、経済的な苦しみからも脱却しているはずです。しかし、リリカが保険適用になっても、患者は治ってはおらず、以前と変わらず病気や生活の苦しさを訴えています。
リリカが保険適用になる前に、大勢の患者が治験に協力しましたが、これは、地獄の苦しみから「治りたい」一念からです。その後の患者の状況をみるにつけ、このときの患者の協力は報われていないと思います。この経過をみても、患者が「自分を治す」ためには、医師や薬に頼らずどうしたらいいかを考え抜かないと、製薬会社を利する結果になるばかりという印象を強く受けます。
ちなみに、私はN医師の治療を受けたことはありません。それは、最初から治せないとわかっているからです。私の場合は薬を飲むごとに激しい副作用が出ていたのに、「薬を飲まないと治らないよ」では、とうてい治すことはできません。また、Bさんの話でわかるように、N医師が私の病気について分かっているとは、到底思えません。ですから私にとって、N医師は名医ではありません。
また、薬なしで治った例には目をつぶり、「FMは治らない」と強引に主張し、社会の弱者として「国から福祉を受ける」という考え方があります。しかし高齢者や生活困窮者などの福祉を国が次々に削っている現在、長期に飲んだ薬で身体がぼろぼろになり困窮したころ、さらに福祉が削られ、自分では自分を救えない「行き止まり」に行ってしまう可能性は十分です。何とかして自力で治っていかないと、希望を持った未来を描くことができません。

|
重症から治った患者が思うこと
重症から治った私が言えることは、治るためにはこれまで医師が教わってきた知識では、とうてい力不足だということです。これは歯科医師も同じです。FMを含む中枢性過敏症候群(CSS)のことを、日本の医師はまだ正確に知りませんし、いわゆる「名医」でさえも、上記のような状態です。
ですから、「線維筋痛症が重症になると、どういう状態になるか」、「最重症からどのようにして治っていくか」は、医師も含め経験していない人には、おそらく、まったく想像もつきません。
この病気の最大の特徴は、「ほんのわずかな刺激で、あっという間に悪くなり、一度悪化すると元に戻るまで非常に長い時間がかかる」ことです。これが、線維筋痛症が難病といわれるゆえんであり、完治するための、最大最高の難関です。
治療行為でさえも悪化への刺激になる可能性があります。このような病気をこれまでの医療は想定しておらず、だから医師たちは、「難病で治らない」と言います。

|
治るにはどうしたらいいのか
まず、線維筋痛症(をはじめとするCSS)は、これまでの医学的常識をはるかに超える病気だということを、医師も患者もよく認識することです。治るにはこれまでの医療の常識を、がらりと変える必要があります。
とくに重症になってしまった場合、治るには健保内の治療では、まず駄目なのです。健保医療で治るなら、とっくの昔に全員が完治しているはずです。
今の医師が習ってきた医療は、表に出た症状を叩く、あるいは抑える対処療法です。それではこの病気に対する治療としては駄目なのです。
治るには、医師が知らない知識を学ぶ、そして病気の本質について学び、自分自身のことを正しく知る。医師が「治せない」という病気ですから、治るには、治った患者の経験や知識を活用することが不可欠です。FMは、確かに困難な病気であり、治った人には、この難しい病気が悪化しないよう、細心の管理をしながら、ついに回復に至った経験と知恵があります。
治った人でなければ、どんな知識が必要かもわからないし、どのようにして、この危険で難しい病気を管理して、回復に向かえばよいかわかりません。
FM(CSS)は、一発で抗生物質が効く感染症のように、短期で治る病気ではありません。回復するのは、「じれったいくらい、ゆっくり」なのが特徴です。
管理が非常に難しく、ちょっとの失敗であっという間に、奈落の底に落ちるように悪化する病気ですから、回復するための仲間も必要です。完治した人も、長い過程では何度も失敗し、どん底を舐めています。応援しあったり相談したりする仲間も大切です。
現状では、医師も歯科医も整体治療家も、まずは治った経験者から、病気の特徴や、FM(CSS)ならではの危険、それへの対策法を学ぶ必要があると思います。線維筋痛症学会も、治った患者から経験と知恵を学び、薬以外のさまざまな方法と、その効果を学び、それらを患者が使いやすいように編成し、健康保険が使えるようにするべきなのですが、そういった患者本位の動きは全く期待できません。
治るための手段はいくつもあり、有効なセルフケアを組み合わせることもできます。
しかし、治るにはまず、病気の知識を得て、この病気の恐ろしい側面をどう克服するかを考えなければなりません。この病気の恐ろしい特徴が克服できないから、多くの人がそれに足を取られて奈落の底に落ちていきます。書店でも情報が入手できますが、手に入る情報は断片的であり、「骨格」の部分が足りません。知識を得て自分自身のことを把握し、「知り得た中から自分に合った手段を選択する」。
医師依存から脱却し、自分自身で学び、考え始めた人にこそ、完治への道が開けます。
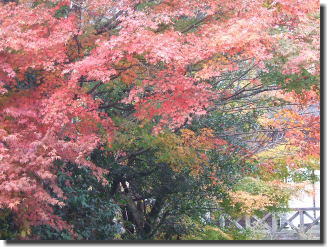
|
私たちの活動
私たちの活動は、世界医師会の大原則、「患者の人権を最優先する」、つまり「知る権利や治る権利」を最優先する活動です。目指すのは「患者の自律」、つまり「患者による自己決定の医療」です。
患者が必要な情報・知識を、会報や資料、講演会などを通じて提供し、患者が自分に合った手段を選ぶ、あるいはセルフケアを覚えるなどのサポートを行い、患者が自分で病気を治していくための支援をしていきます。
|
世界医師会の「医の倫理規定:患者の自律」とは 「医師から自立し、患者自身が知験や治療に関するさまざまな決定を自分で行っていく」 「お任せ(パターナリズムの医療)から、自己決定の医療へと自立する」 |
NPO市民健康ラボラトリーの活動方針・・・「患者の人権最優先」
- 「患者は病気や治療に関して、マイナス情報も含むあらゆることを知る権利がある」「治療を選ぶ権利、拒否する権利がある」ことを確認する。
- 世界医師会が採択した「患者の自律」のためのサポートを行う。
- 患者自身が「治療に関する自己決定を行う」ときの助けになる、病気や治療のマイナス面を含むさまざまな情報を提供し、患者が「自己決定の医療」を行うサポートをする。
*「病気や治療に関するあらゆること」には、海外の研究や論文など、日本以外の研究者や患者が共有する知識・情報も含まれる。 - NPO市民健康ラボラトリーは、患者が「自己決定の医療」を行う際に、「患者自身の判断や選択、考えを妨げない」「治療方針の決定は、あくまで患者自身が行う」ものとする。

|
*すべての患者さんへ
患者の側に立ち、がん三大治療の危険性を啓蒙し続けている医師の近藤誠さんが書いた「近藤誠の女性の医学」という本があります。
この本のなかに「僕が出会った患者さんたち」というとても興味深い記事があります。
近藤さんが出会った患者さんたちは、自分の価値観や、自分が望む生き方をしっかり把握し、自分の意思で治療を選択しています。患者さんや家族が、担当医師が言う以外の治療法を情報収集し、その中から、患者さんが自分で納得し、自分で決定した治療方針を選ぶという生き方をしています。
そして近藤さんは、患者さんのQOLにとってよいと判断する治療方針を示し、しかし、無理強いはせず、最終決定は患者さんの意思にゆだねています。
近藤さんは、医薬利権とは関係なく、患者さんを自分の研究のためのモルモットにはしていません。近藤さんの患者さんは、人間としての尊厳が保たれていることが感じられます。
近藤さん自身は、以下のように言っています。
「逆境にもめげず、自分で治療法を選び取ってきた女性たちは、その結果が自信となり、その後の人生も、明るく前向きに送られています。むしろ男性のほうが、既存の枠にとらわれたり、社会的立場を気にして、いいたいこともいえなくなってしまいがち。女性たちよ、どうぞ男たちをリードしていってくださいね。
・・・社会を変えていく力は、女性のほうにこそあるはずです。生活の中で養った女性のカンを働かせ、理不尽な医療には「ノー」と声をあげましょう。医療改革の鍵は、女性が握っているのです」
再度言いますが、世界医師会は、「患者の人権」を患者自らが守るため、「患者の自律」を採択しています。「お任せ(パターナリズムの医療)から、自己決定の医療へと自立しなさい」
「医師が言うからその通りにした。医師が薬を処方したから、薬を飲んだ」
その結果、「治る」希望はかなわず、薬依存になり離脱症状に苦しんだとすれば、「医師は患者の人権を最優先したのか」という大問題とともに、患者自身も「自己決定の医療へと自立しなかったから、「自分の人権」が守れなかった」ともいえます。
医師が「患者の人権最優先」でない場合、患者は「自律」し、医師から「自立」した存在になることで、自分の人権を守り、回復への自助努力をしなければなりません。
NPO市民健康ラボラトリーは、病気や回復に関するさまざまな情報を収集し、それを患者さんに提示し、患者自らが自分に合った方法を選び、「自分が自分の主治医」となって回復に向かうためのサポートを行います。つまり、世界医師会が定める「患者の自律」のための活動をしています。
|
*Bさんの後日談 文中で、ガンと診断されたCS患者のBさんは、後日、ガンは誤診であったと分かりました。 Bさんは誤診のおかげで、CSの上にFMまで発症という深刻な事態を招いてしまったわけです。じつは、CS患者のガン発症例は、ほとんど聞いたことがありません。CS患者が多様な化学物質を避けざるを得ない毎日が、ガン原因の化学物質を避けることにつながり、ひいてはガンが減ることにつながるのではないかと感じます。 その逆に、Bさんのように、ガン治療で抗癌剤や放射線治療を受けたら、その後、FMやCSを発症したという例は、患者さんからかなり聞きます。治療による化学物質などの継続した暴露が、CSSの発症リスクになっていることを感じます。 |

|
「患者の人権」に関する資料(医師が「患者の人権を最優先」するための必須知識)
1.人権について
「人権」とは、人が誰でも生まれながらに持つ天賦の自然権。基本的人権はあらゆる国内法より上位かつ不可侵であり、基本的人権には知る権利も含まれる。(国連の「世界人権宣言」参照。この優先順位が日本国憲法にも反映されている。)
2.世界医師会(WMA)が採択した「医の倫理規定」
世界医師会は各国医師会の連合体であり(日本医師会も加入)、世界医師会が戦後に採択した「医の倫理規定」の大原則は「患者の人権最優先」である。
・世界医師会は戦後、国連と歩調を合わせ、「人権最優先」を、あらゆる国内法より上位かつ不可侵と位置づけた。
3.世界医師会が求める「患者の人権最優先」とは
医師は、人間の尊厳に対する共感と尊敬の念を持って、専門的・道徳的に完全に自律の状態で、適切な医療の提供に検診しなければならない:医の国際倫理綱領1949年
「医師は、患者の人権を(国や製薬会社など)第三者の意向より優先する」
(これの意味するところは、「医師は患者の人権を最優先(擁護)するため、悪法には従わない。医師は患者の人権を擁護するため、時の権力の意向(現行法)を超える責任がある。)
「医師は、人命に対して最大限の尊敬(畏敬の念)を持ち続ける責務を、心に銘記しなければならない」
「医師は、医療の現場においては、患者の人権(マイナス情報も含む、治療に関するあらゆることを知り、治療を選ぶあるいは拒否する権利)を最優先する。治療を行う際は、医師は治療の危険も含めたあらゆることを充分に患者に説明し、かつ患者の(誰にも強制されない)自主的な合意が必要とされる」
4.世界医師会が採択した「患者の自律」
世界医師会は、患者自身の人権を守るために、「患者の自律」を採択している。
「患者の自律」とは、患者が二度と、戦時中ナチス医師によって行われたような人体実験の道具とならないために、「医師から自立し、患者自身が知験や治療に関するさまざまな決定を自分で行っていく」「お任せ(パターナリズムの医療)から、自己決定の医療へと自立しなさい」との意味
Patient autonomy which means that patient shoud be the ultimate decisionmakers in matters that affect themselves (WMA Mecical Ethics Monual 2005:世界医師会「医の倫理規定」2005年)
訳:「患者に影響を及ぼす事項については、患者が最終的な意思決定者であるべき」

|
